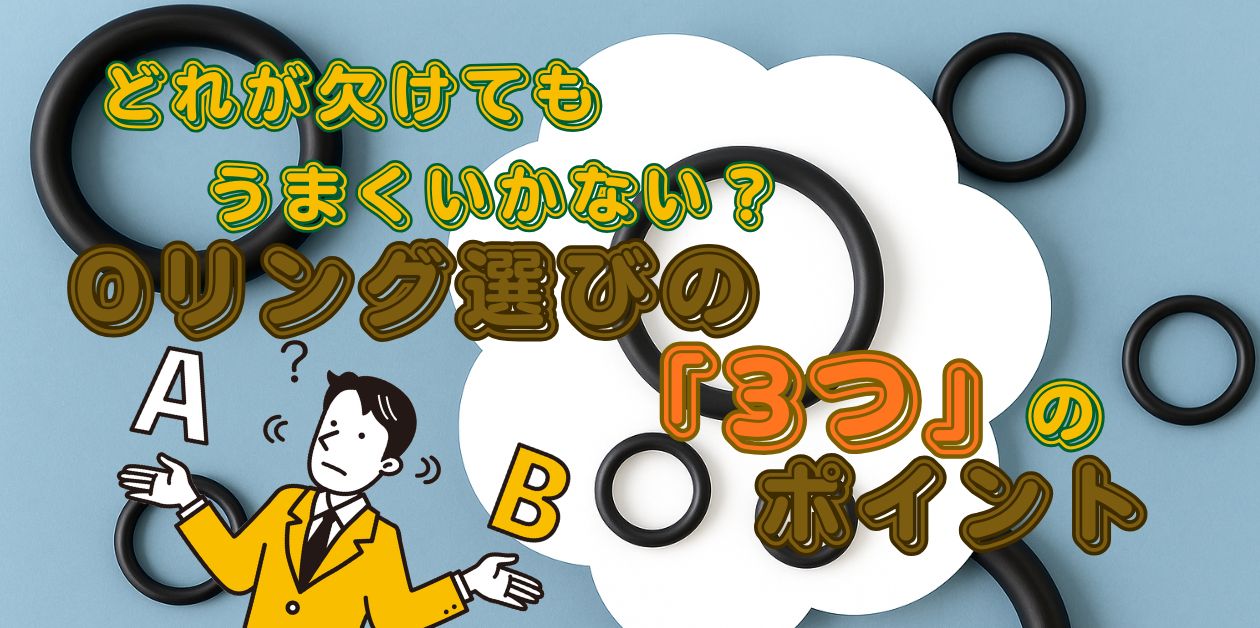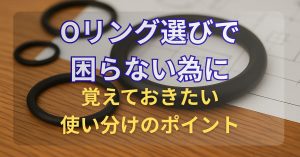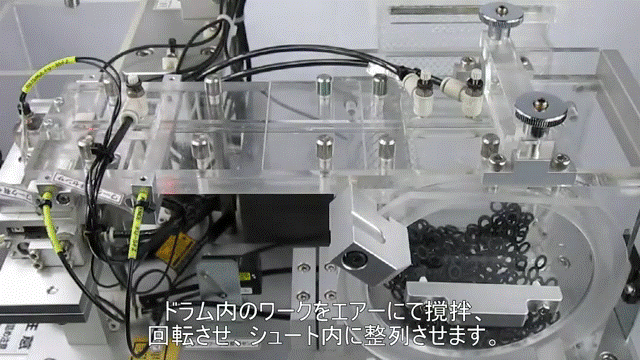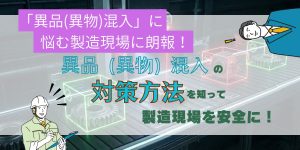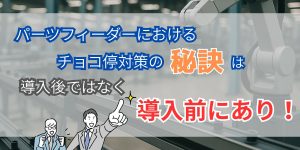シール材として知られている「Oリング」ですが、選定の際にはどんなことに気を付けていますか?
Oリングは「流体をシール(密封・密閉)する」用途として使用されるため、機械の重要な役割の部分に使われることが多いと思います。
具体的に取り付けたい部分が決まっていれば、だいたいの大きさまでは決まってきますが、Oリングの選び方(材質や種類など)の判断を間違えてしまうと、シール性が保てなくなり、機械として成り立ちません。
今回の記事では、「どのような考え方」でOリングを「選定」すればよいのかについて解説していきます。
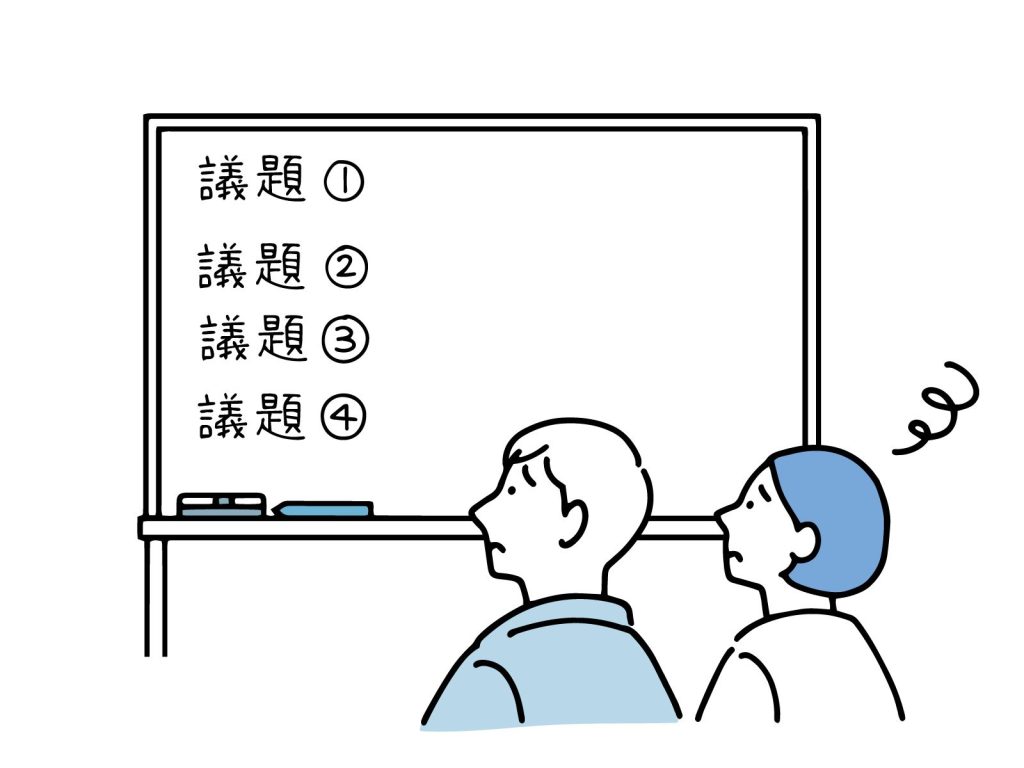
1.Oリングとは?
そもそも、『Oリング』とはどのようなものなのでしょうか?
まず、Oリングは「シール材」として活用されており、「運動用(パッキン)」と「固定用(ガスケット)」の両方の機能がある為、シール材を選定する際には、”まずは「Oリング」”を検討することが多いです。
『Oリング』に関する内容は、別記事にて解説しています。
Oリングの「特徴」としては下記のようなことがあげられます。
・コンパクトであるため、装着するにあたって場所をとらない
・着脱が簡単なため、メンテナンスしやすい
・種類が豊富なため、選定しやすく、規格品は入手しやすい
・他のシール材より比較的安価
「規格品の種類が豊富」な為「選びやすく」、サイズも「コンパクト」なので「設計検討しやすい」ですね。
2.Oリングの選び方について
Oリングには様々な規格や材質があり、それぞれの組み合わせによって、用途が変わってきます。
Oリング選定のプロセスについて、順を追って考えていきましょう。
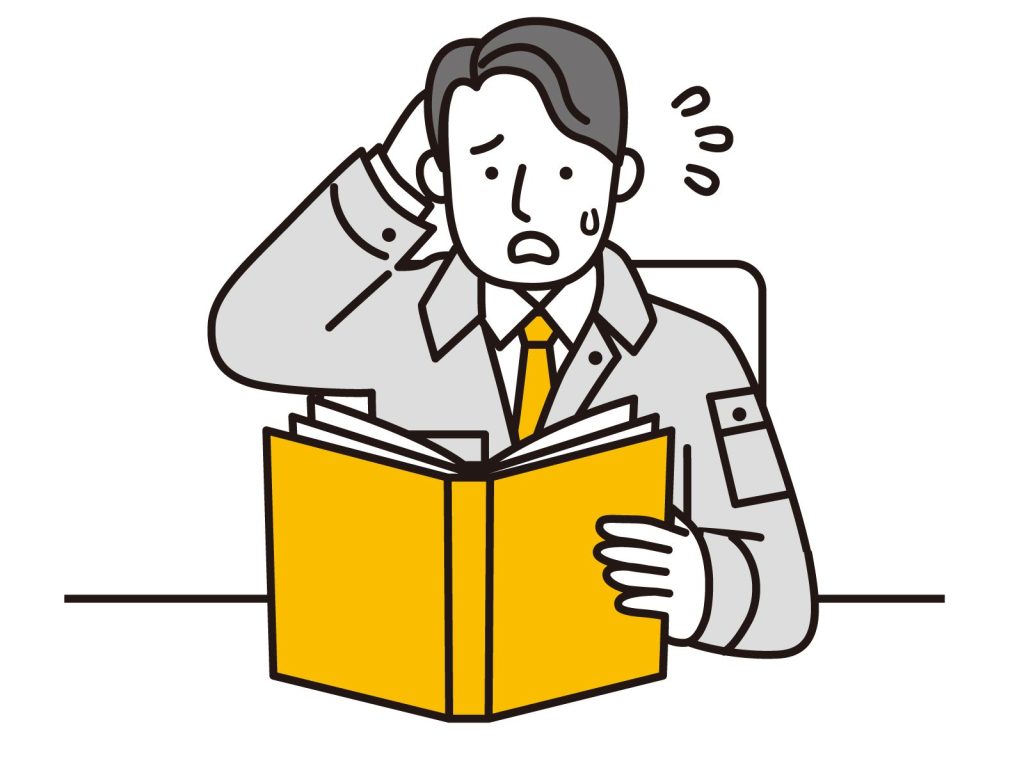
A. 機能
1つ目に検討したいことは「どのような機能を持たせたいか」ということです。
使用用途を想像することによって、「どの規格のOリングを使いたいのか」を決定していきます。
具体的にいくつか例をあげてみます。
このような用途で使用する場合はどのようなOリングを選んだらよいのでしょうか?
「部品を連結させ流体経路を設けたい」などの「耐圧性」が求めれれる場合には、
「P規格」や「G規格」が候補としてあげられます。
「ピストン運動する部位で使いたい」場合は、運動する部位で使用するため、
「運動用」である「P規格」が適していると考えられます。
「配線コネクタ接続部で使いたい」場合などは、「固定部分」であり「小型精密機器」
でもあるため、「S規格」がよいのではないでしょうか。
上記の具体例のように用途によって最適な規格を選んでいきます。
Oリングの規格ごとに特徴があるので、まずはそれぞれの規格が「どんな特徴」なのかを知っておくことで、規格を選定しやすくなります。
B. 使用環境
2つ目に検討したいことは「どのような環境で使用したいのか」ということです。
使用環境が分かれば、「どんな材質のOリングを使えばいいのか」を選択することができます。
材質によって得意な環境が異なる為、Oリングの破損や劣化のリスクを避けるためにも、
「流体」「温度」「圧力」の観点から材質選びをすることが重要です。
考慮しなくてはいけない使用環境は次通りです。
「どのような流体(液体や気体)に接するのか?」
「どのような温度環境で使用するのか?」
「どの程度の圧力がかかる部位に組み付けるのか?」
まずは「どのような流体(液体や気体)に接するのか?」について考えていきましょう。
『油』に接する場合は『耐油性』の素材、例としては、ニトリルゴム、フッ素ゴム、ウレタンゴムや水酸化ニトリルゴムなどがあげられます。
『化学薬品』に接する場合には『耐薬品性』の素材を選ぶ必要があり、例としては、フッ素ゴムやフッ素樹脂などが候補となります。
次に「どのような温度環境で使用するのか?」について考えていきましょう。
『熱い環境』の場合は『耐熱性』の素材、例としては、フッ素ゴム、シリコンゴムなどが考えられます。
『寒い環境』の場合は『耐寒性』の素材、例としては、シリコンゴムやエチレンプロピレンゴムなどを選択します。
最後に「どの程度の圧力がかかる部位に組み付けるのか?」について考えていきましょう。
『圧力のかかる環境』で使用する場合には『耐圧性』の素材、例としては、ウレタンゴムや水酸化ニトリルゴムなどがあげられます。
『摩耗する箇所』で使用する場合には『耐摩耗性』の素材、例としては、ニトリルゴムや水酸化ニトリルゴムなどがあります。
ここまでは、使用する「環境」について個々に考えてきましたが、実際に使用する環境は、「流体」「温度」「圧力」それぞれの条件が組み合わさることになります。
「どんな環境」で使用するのかをより『具体的に想定』することによって、最適な材質を選ぶことができます。
C. サイズ
3つ目に検討したいことは「どのくらいのサイズにしたいのか」ということです。
Oリングを組み込みたい部位を設計し、シールしたい部分を「どのような状態にしたいのか」を考えていきます。
基本的には「運動用」「固定用」両方の機能を持っている『P規格』から組み込みを検討していくと自社の在庫や設計の標準化の点で管理し易くなりおすすめです。
組み込む部分の「スペース」や「機能」によって規格を変更した方が良いのかを検討していきます。
下記では、P規格を基準として設計を進める場合の規格変更についていくつか例をあげてみます。
径の大きい部位をシールする際にP規格でスペース的に対応できない場合は、P規格から「G規格」に変更することでコンパクトな設計とすることができます。(線径を細くし、スペースを削減するため)
小さな部品へシールが必要な場合は、P規格から「S規格」に変更し、より省スペース化をはかることができます。
運動部で「動きを軽くしたい」場合には、「ゴミが入らなければ良い程度のシール」・「圧力のかからない場所」などの条件が合えば、つぶし代を推奨値より少なく設計することで運動部の操作性や負荷を軽減でき、安価に目標が達成できます。
シール材を選択する際には、「入手性」や「設計規格」などの選定環境によって判断する場合も多くなりますが、Oリングを「選択する考え方」を持っていれば、検討もスムーズに進みやすいですね。
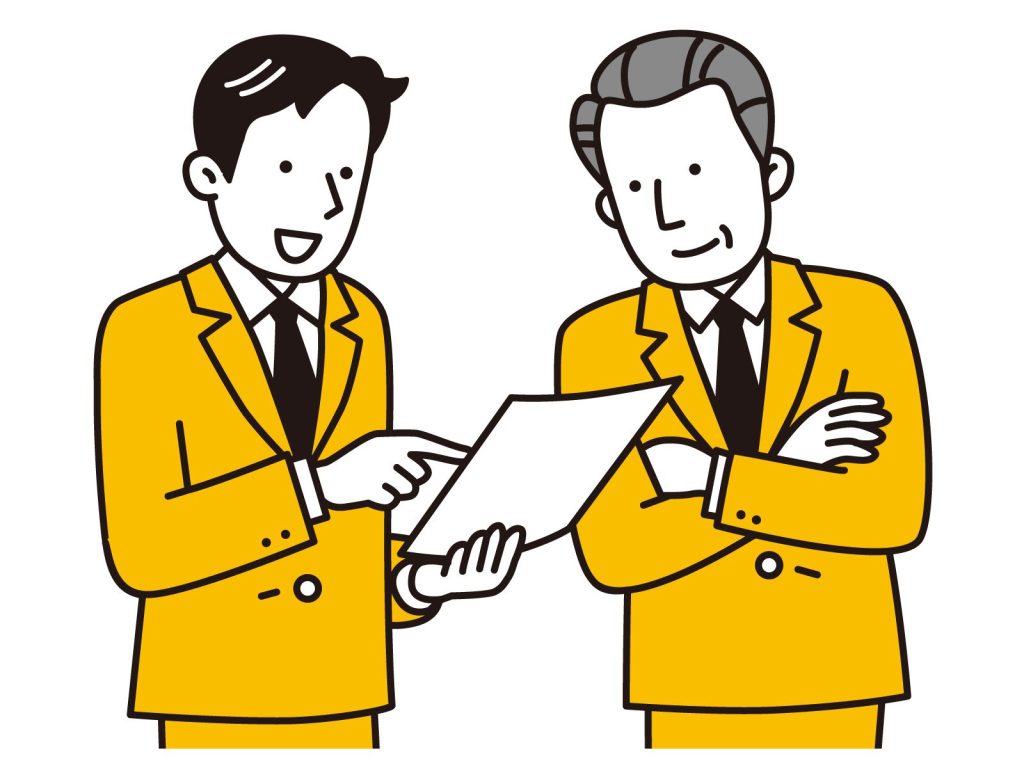
3.まとめ
今回は「Oリング選び」の「考え方」について解説してきました。
Oリング選びには「3つ」の視点があり、どれか1つでも欠けてしまうと「シール性」が保てなくなり、製品として成り立ちません。
製品そのものや、使う環境など様々な状況を想定し、最適なOリングを選ぶ必要があります。
選定における「3つ」の考え方を念頭に置き、最適なOリングを選んでいきましょう。
「手組みじゃ、もう回らない…」 そう感じたことはありませんか?
Oリングを 1つずつ確実に 供給しながら、作業ミス・人的コストを削減 できる方法があります。
弊社が開発した「Oリング整列供給ユニット」は、幅広いサイズ・材質のOリング供給に
対応した実績を持つ専用装置です。
※ダウンロードフォームより供給実績ご確認できます。
※切り出し装置はイメージです。弊社では取り扱っておりません。
書いた人:平野 遼香
Oリング整列供給ユニット 営業窓口担当。パーツフィーダーについて日々勉強中。ユーザーのみなさんが “知りたいこと” をお伝えできるよう、学んだ内容を情報発信していきます!最近ハマっていることは、コッペパン作り。