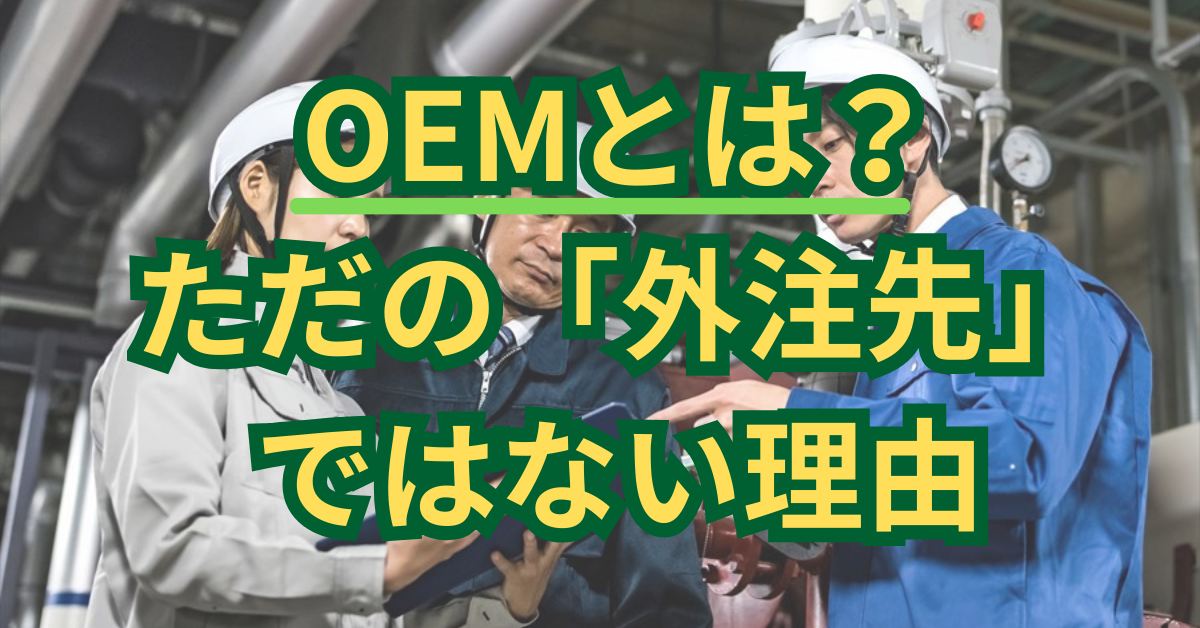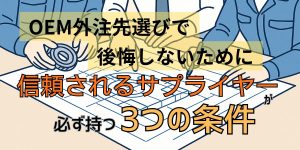ものづくりの世界でよく耳にする「OEM」。
「外注と同じことかな?」と思われがちですが、実はOEMはただの製造委託ではなく、会社の成長を支える大事な仕組みです。
OEMをうまく活用すれば、コストを抑えたり、生産の効率を上げたりしながら、自社の強みをもっと伸ばすことができます。
その一方で、品質の管理や委託先の選び方など、気をつけるべきポイントもあります。
この記事では、「OEMとは何か?」という基本から、OEMの種類、メリットとデメリット、そして信頼できるパートナーをどう選べばよいかまで、詳しく説明していきます。
OEMとは?
「OEM」とは「Original Equipment Manufacturer(オリジナル・イクイップメント・マニュファクチャラー)」の略で、日本語では「相手先ブランド製造」と訳されることが一般的です。
簡単に言うと、A社が企画・設計した製品をB社が製造し、最終的にはA社のブランド名で販売されるというビジネスモデルです。
例えば、自動車メーカーが部品メーカーに特定の部品製造を委託したり、家電メーカーが他社から製造依頼を受けたりするケースがこれにあたります。
経済産業省が公開している「セット版OEMガイドライン(製品安全分野)」では、OEMに関連する事業者を
「供給先=製造委託元・販売元」と位置づけています。
つまり、ブランドを持つ企業が委託元、製造を担う企業が受託先という関係性が、公的な視点からも整理されています。
(出典:経済産業省「セット版OEMガイドライン(製品安全分野)」
https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07_shouan_guideline_3.pdf)
OEMを「下請け」と混同されることがありますが、両者には大きな違いがあります。
OEMは単なる下請け生産ではなく、対等なビジネスパートナーとしての関係性が特徴です。
OEMパートナーは高い技術力や品質管理能力を持ち、時には製造工程の改善提案も行う戦略的なパートナーとして位置づけられています。
では、次にOEMにはどのような種類があるのか?について詳しく見ていきましょう。
OEMの種類
製造業におけるOEMには、委託内容や範囲によっていくつかのパターンがあります。
具体的には、
どんなことをお願いするのか?
どの範囲まで任せられるのか?
ここでも、様々な悩みがあると思います。
まずは、今困っている・助けてもらいたい部分は何なのか? を確認することが大切です。
では、「OEM」には主にどんな場合があるのかについて確認していきましょう。
一部工程だけを請け負う
1つ目は、設計やデザインは委託元が行い、製造工程の一部だけをOEMメーカーに委託するパターンです。
例えば、金属加工や塗装、組立など特定の工程だけを外部に任せるケースがこれにあたります。
部分的な生産委託とも言えるでしょう。
このタイプのメリットは、自社の得意分野に集中しながら、自社で技術的に難しい工程や設備投資が必要な工程だけを外部に任せることができる点です。
例としては、精密機械メーカーが複雑な金属加工だけを専門業者に委託したり、電子機器メーカーがプリント基板の実装だけを委託したりすることがあげられます。
部品製造から組立までを請け負う
2つ目は、製品の部品製造から組立まで一貫して委託するパターンです。
委託元は基本設計や仕様を提供し、実際の製造工程のほぼ全てをOEM製造メーカーが担当します。
このタイプでは、委託元は製造設備や人員を持たなくても、自社ブランドの製品を市場に投入できるというメリットや加工から塗装・組立・検査までを一貫して任せることによって、工程間の連携もスムーズになります。
例としては、スタートアップ企業が自社開発した製品の量産を大手製造業者に生産委託するケースや、複数の製品ラインを持つメーカーが 特定製品の製造を全て外部に委託する ケースなどが該当します。
ここまで、OEMの種類について確認してきました。
自社での困っているポイントによって、何を任せたいのか?どこまで依頼したいのか?が見えてきます。
次に、OEMを導入する前に確認すべきメリット・デメリットについて整理します。
OEM委託することのメリット
自社でしかできない仕事に集中できる
OEMの大きなメリットの一つは、自社が最も得意なことや強みに、人やお金、時間といった大切な資源を集中して使えることです。
製造を外部に委託することで、本来注力すべき業務に対して、より多くの時間とエネルギーを投入できるようになります。
例えば、製品開発力が強みの企業なら研究開発により多くのリソースを投入でき、営業力が強みの企業なら市場開拓や顧客関係構築に集中できます。
製造を専門とする会社に任せることによる品質保証
OEMのもう一つの大きなメリットは、製造のプロフェッショナルが持つ専門性やノウハウを活用できるという点です。
製造に特化した企業は、最新の設備や技術、効率的な生産方法を常に追求している為、自社で工数やコストをかけることなく、成果を得ることができます。
中小企業にとっては、自社では実現困難な高度な製造技術や品質管理システムを持つOEMパートナーと協力することで、製品品質の向上につながります。
設備投資や人材投資のコスト抑制
そして、OEMの直接的なメリットとしては、大規模な製造設備への投資や製造人材の採用・育成コストを抑制できるということがあげられます。
製造業では、最新設備の導入や工場スペースの確保、熟練技術者の育成には多大なコストと時間がかかります。
製造を得意としている会社には、すでに力量のある人材や技術がある為、効率的に製造を進めることができます。
ここまで「OEM委託することのメリット」について見てきましたが、一方で、OEMには 注意すべきデメリット もあります。
次は「OEM委託することのデメリット(注意すべき点)」について確認していきましょう。
OEM委託することのデメリット
品質管理の難しさ
OEM委託における課題の一つは、自社生産と同等の品質をOEMパートナーで実現することの難しさです。
同じ図面や仕様書に基づいていても、製造環境や作業者のスキル、使用する設備によって品質に差が生じることがあります。
製品が複雑であったり、高い精度が必要であればあるほど、この問題はより大きく現れてきます。
対策として、詳細な品質基準書の作成 や 定期的な工場監査、初期ロットの厳格な検査などが必要となり、製造委託先との綿密なコミュニケーションが重要となってきます。
高度な技術要求への課題
製造業において、特に高度な技術やノウハウを要する製品は、製造委託が困難となる場合があります。
匠の技が必要な製品や、自社の独自技術が必要となる製品は、外部委託によって品質や競争力が損なわれるリスクがあります。
対策としては、技術の難易度に応じた段階的な委託や、核となる工程のみ自社に残す「部分生産委託」などが考えられます。
安心して製造を任せることができるパートナーを探せるかどうかが、成功のカギになります。
期待と現実のギャップ
製造委託における大きな課題として、委託元の期待と実際の製品との間にギャップが生じることがあります。
このギャップの主な原因は、「言語化していない暗黙の了解」が委託先と共有できていないことにあります。
製造業では、図面や仕様書に明記されていない「当たり前」の品質基準や、業界特有の常識が多く存在します。
このギャップを埋めるには、詳細な仕様書作成、サンプル品の共有なども重要ですが、いかにコミュニケーションを綿密に取れるか・認識のギャップが埋めるまで根気よく向き合えるかが大切です。
社外へ依頼する時の課題は、やはり「認識の違い」の部分が大きいです。
この問題を解消する方法が、「信頼できるパートナー選び」となります。
それでは、どのように「信頼できるパートナー(製造委託先)」を選べばよいのでしょうか?
信頼できるOEM委託先の選び方
現場確認を徹底する姿勢
良いOEMパートナーの特徴の一つは、現場確認を徹底的にしているということです。
図面には書かれていない「暗黙の前提」や「業界特有の常識」を製品に反映できることはもちろんですが、
「OEM委託元」の求めていることを深く理解しようとする「OEM委託先」を見つける
ことが重要となってきます。
優れた製造委託先は、製品の使用環境の確認や過去のクレーム履歴のヒアリングなど、受注前に詳細な現場確認を行い、形式的な図面確認だけでなく、製品の本質的な要求を理解しようとする姿勢を持つパートナーを選ぶことこそが、成功への第一歩です。
「できる/できない」を明確にする誠実さ
信頼できるOEM製造パートナーの重要な特徴は、「できること」と「できないこと」を明確に伝える誠実さです。
何でも「できます」と言うパートナーより、
技術的に困難な要求には代替案を提案し、コストと品質のバランスについて率直に議論できる
パートナーを選びましょう。
「できない」ことを正直に伝えられるパートナーこそ、「できる」ことに責任を持てるパートナーであると言えます。
品質基準を事前にすり合わせる重要性
製造委託の成功には、委託元と委託先の間で品質基準を細部まで事前にすり合わせることが不可欠です。
「良品」の定義が委託元と委託先で異なると、後々トラブルの原因となります。
検査基準書の作成と共有、測定方法の統一、初期ロットの評価プロセス確立などを通じて、
品質に対する認識が合致するまで、徹底的な確認・綿密なすり合わせができる
パートナーを見つけ出すことが重要です。
品質基準のすり合わせは継続的なプロセスであり、そのための時間と労力を惜しまないOEM製造パートナーを選びましょう。
一貫対応できる製造体制の利点
製造委託先選びでは、加工から塗装・組立・検査までを一貫して対応できる体制も重要なポイントです。
複数の工程を一社で対応できるということは、
「工程間の連携」「品質」「納期」をまるごと管理してもらうことができる
そんなOEM製造パートナーがいれば、安心して背中を任せることができます。
複数の工程を一貫して対応できる体制は、やり取りの手間や時間の節約と品質の安定化につながります。
まとめ
ここまで製造業におけるOEMについて、基本概念から種類、メリット・デメリット、そして信頼できるパートナー選びについて詳しく見てきました。
OEMは、上手に活用すれば製造業の会社に大きなチャンスをもたらす大切な経営の選択肢であり、多くの企業の成長戦略となっています。
OEMを検討する時には、まず、自社でしかできないことをきちんと分析し、「自社の強みを明確にする」ことが重要です。
そして、自社製品の製造を任せることができる「OEMパートナー」を見つけ、
「お互いを信用して仕事ができる関係」「綿密に確認し合うことの大切さ」「品質を常に確認する姿勢」
という3つのポイントを忘れずに進めていくことが OEM成功の近道 となります。
OEMは「ただ作ってもらう」という単純なものではなく、会社の成長を支える大切な戦略です。
自社の強みを最大限に活かし、信頼できるOEM製造パートナーと一緒に進むことで、製造委託を通じて会社を着実に成長させることができます。
皆さまの会社が製造委託によって新たな可能性を見つけ、さらに発展していくことを願っています。
こんなお悩みありませんか?
多くの製造業の経営者や実務担当者が、こうした課題に直面しています。適切なOEM製造パートナーを選ぶことで、これらの問題を解決し、一貫対応による生産効率化を実現することができます。
サイダ・UMS のOEM事業 では、「お客様と真摯に向き合い、品質の高い ものづくり 」に取り組んでおります。
サイダ・UMS の「OEMパートナー」である下記企業の 実例付き資料 はこちらからご確認いただけます。
・コマツNTC株式会社
・スター精密株式会社
・株式会社和井田製作所
・碌々スマートテクノロジー株式会社
\\ 信頼できるOEMパートナー選びについて詳しくはこちら //
※ダウンロードフォームより実績事例付き資料のダウンロードができます。
書いた人:平野 遼香
自社商品「Oリング整列供給ユニット」営業窓口担当。製造業について日々勉強中。ユーザーのみなさんが “知りたいこと” をお伝えできるよう、学んだ内容を情報発信していきます!最近ハマっていることは、鶏ハムづくり。